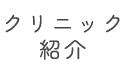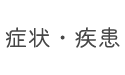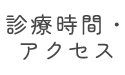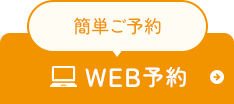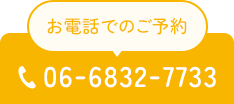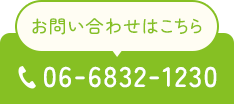当院の小児科について

発熱がある方へ
- 発熱がある方は、来院前に必ずお電話でご連絡いただき、指定された時間にご来院ください。
- 院内感染防止のため、当クリニックでは、これまで基礎疾患のある方や発熱・咳などの症状がある方には、別の入り口から入っていただき、隔離室での待機をお願いしております。今後も感染予防を徹底するため、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
アレルギー科
アレルギーは、体を守るはずの免疫反応が無害なものに反応したり、必要以上に強く反応してしまったりして様々な症状が引き起こされる状態です。当院では、アレルギーが原因で発症する気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎・花粉症、蕁麻疹などの診断と治療を行っています。アレルギーに関する症状でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
病児保育室・シックキッズ
お子様が病気の回復期にあり、集団保育が難しい場合や、薬の投与が必要な場合に、医師の判断で利用できる保育室を提供しています。申し込みから利用までの手順については、
「吹田市病児・病後児保育室利用のしおり」や「7.ご利用方法」を参照してください。
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018219/1018220/1005682.html
※定員に余裕がある場合でも、お子さまの症状によっては、ご利用いただけない場合がございます。
小児科で診察可能な症状
熱が下がらない
子供はまだ成長途中で免疫が大人に比べて未熟なため、発熱しやすく、熱が3〜4日間持続するケースも少なくありません。熱が4日以上続く場合、またはそれ以上に長引く場合、単なる風邪の症状が長引いている可能性もありますが、肺炎や中耳炎などの合併症、または川崎病などの他の疾患が原因であることも考えられるため、軽視は禁物です。
子どもの鼻水がとまらない
鼻水や鼻づまりは風邪やアレルギーの一般的な症状で、鼻水は体がウイルスや細菌を排出しようとする反応、鼻づまりは鼻を通る空気の流れが悪くなって起こる感覚で、原因は鼻の中の粘膜の腫れとそれ以外を分かれます。透明から白っぽい鼻水で他の症状がまったくなければ、すぐに受診せず様子を見ても大丈夫です。
鼻水や鼻づまりを軽減するには、湿度を保つ、鼻水吸引をするなどが有効です。しかし、鼻水が黄色や緑色で長期化している場合は細菌感染や中耳炎、副鼻腔炎の可能性があり、早期治療が必要です。また、鼻水や鼻づまりは子供の集中力低下や口呼吸の原因になるため、要注意です。
子どもの咳が止まらない・長引く
咳は風邪や喘息などの症状の1つであり、気道に入ったウイルスや異物を体外に排出するための自然な反応です。
咳の種類には「コンコン」「ケンケン」「ゼーゼー」といった様々な音があり、これらの特徴から疾患の原因や状態を推測することができます。ただし、咳が3〜4週間以上続く場合は、単なる風邪以外のアレルギー疾患や感染症が原因である可能性が高まります。治療を受けていても咳が改善しない場合は、別の疾患が潜んでいる可能性があるため、早めに医療機関への受診が必要です。
当院では、咳以外に発熱や発疹などの症状の有無、同じ症状を持つご家族の有無なども確認し、感染症やアレルギーの検査を通じて原因を探っていきます。お子様が服用中の薬に関する情報も重要ですので、受診時にはお薬手帳や薬の容器をお持ちください。必要に応じて、感染症の検査、アレルギー検査、X線検査(いわゆるレントゲン検査)へご案内します。
嘔吐・下痢が続く
お子様が嘔吐や下痢を経験すると、親御さんは心配されることでしょう。多くの場合、適切なケアと経過観察で改善が見られますが、吐き気が続く場合は自己判断せずに医療機関での診察を受けることが重要です。
発熱や嘔吐・下痢が続き、お子様がぐったりしていたり顔色が悪くなったりした場合は、迷わずに受診しましょう。また、ウイルス感染が原因の嘔吐の場合は、脱水症状を引き起こす可能性が高いため、こまめな水分補給を心がけましょう。症状が悪化している場合やなかなか治らない場合は当院へご相談ください。
胃腸炎
ほとんどは、ウイルスや細菌による感染性胃腸炎です。具体的な病原体としては、ロタウイルス、ノロウイルス、アデノウイルス、腸炎ビブリオ、病原性大腸菌、サルモネラ、カンピロバクターなどが挙げられます。
主に、吐き気・嘔吐、下痢、発熱、腹痛などの症状が見られます。脱水症状、家族への感染にも注意しなければなりません。また乳児の場合、けいれんを伴うこともあります。
症状を和らげ、脱水・感染拡大を予防するための対処法も指導いたしますので、安心してご相談ください。
発疹
発疹は、肌に現れる見た目の変化全般を指します。子供に見られる病気で、発疹が特徴的なものには多数あります。
これらは、手足口病、溶連菌感染症、突発性発疹、はしか、風疹、水ぼうそう、とびひ(伝染性膿痂疹)といった感染症や、じんま疹、アトピー性皮膚炎といったアレルギー反応、出血斑のような血液の病気によるものに分けられます。
発熱の有無や発疹の部位、発疹の様子をみて診断をすすめ適切な対処法をお伝えいたします。もちろん当院で治療困難な場合には近隣の信頼できる皮膚科に紹介をさせていただきますので、お困りの際は安心してご相談ください。
頭痛・疼痛
子どもの頭痛は、基礎疾患のない(ほかに症状がない)一次性頭痛(片頭痛や緊張型頭痛など)と基礎疾患を有する(ほかにも症状がみられる)二次性頭痛に大別されます。一次性頭痛がほとんどで、通常は安静・休養によって痛みは引きます。必要に応じて、鎮痛剤なども使用します。
意外に思われるかもしれませんが、副鼻腔炎の症状として頭痛が起こるということもあります。副鼻腔炎は長引かせると慢性化することがありますので、注意が必要です。
小さな子どもは、頭痛などの自覚症状を正確に訴えることができません。不機嫌が続くなど、様子の変化も注意して観察し、気になった時にはお気軽にご相談ください。
不眠や過眠・起きられない
学童期前後に見られる睡眠障害としては、不眠(入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒など)、過眠(主に起床困難とされる)、夜驚症、夢中遊行などが挙げられます。発達障害やPTSD(いじめなどを含む)、喘息、アトピー性皮膚炎、むずむず脚症候群などの疾患をはじめ、愛着障害や塾やスポーツなどによる多忙などによって、不眠に陥ることもあります。過眠には、ナルコレプシーのような睡眠システムの異常や、過度な活動による睡眠不足、周期性過眠症などがあります。
夜驚症は、深い睡眠中に恐怖体験のような叫び声や心拍上昇を伴うことが多く、就学前後によく見られます。夢中遊行は、深い睡眠中に複雑な行動を示すものの、周囲の呼びかけには応答せず、起床後に記憶がない状態です。
夜驚症や夢中遊行の背後には、てんかんの複雑部分発作が隠れている可能性もあるため、放置は禁物です。
朝起きられないなどは起立性調節障害(OD:Orthostatic Dysregulation)の典型的な症状の1つです。ODは自律神経系の不調からくる身体の病気で、不登校の原因にもなってしまいます。睡眠や朝起きられないなどの問題があれば放置せず、お気軽にご相談ください。
夜尿症
5歳以上の子どもが1カ月に1回以上おねしょをしてしまう状態が3カ月以上続くことを「夜尿症」と言います。
夜尿症は5~6歳で約20%、小学校低学年で約10%、10歳を超えても5%前後にみられ、中学生になると1~3%まで減少しますが、成人になっても残存する場合があります。
多くは、排尿や水分補給に関連する習慣を含めた生活習慣の改善によって、頻度を減らすことが可能です。また必要に応じて、積極的治療(夜尿アラーム療法や薬物療法)を行います。
おねしょをした時のご家庭での対応にも難しさがあるかと思います。お子様の症状・状況に合わせた対応をご説明しますので、気になる場合はお気軽にご相談ください。お子様の心情面にも十分に配慮した診察をいたします。
のどの痛み(咽頭痛)
子どもでよくみられる、のどの痛みは主にウイルスや細菌による感染症が原因です。代表的な疾患として、アデノウイルスやインフルエンザウイルス、コクサッキーウイルス、溶連菌感染症などが挙げられます。
ウイルス性の咽頭痛は自然に治ることが多いですが、細菌性の溶連菌感染症はリウマチ熱という合併症を予防するためにも抗生物質が必要です。のどの痛みは、乾燥やアレルギー、逆流性食道炎などが原因となることもあります。症状が長引いたり、発熱や呼吸困難を伴ったりする場合は、医師の診察を受けることをお勧めします。
小児科で診察可能な疾患
風邪(感冒)
「風邪(感冒)」は、くしゃみ、鼻水、咳、喉の痛みなどの症状がみられる急性のウイルス感染症です。ウイルスが鼻や喉の粘膜に感染して炎症を引き起こすことが原因で、多種多様なウイルスが関与しています。ウイルスが原因であるため、特定の治療薬は存在せず、症状を緩和する薬を用いて、体から自然にウイルスが排除されるのを待つのが一般的な治療法です。
扁桃炎
扁桃炎は、喉の奥に位置する扁桃(左右にあるリンパ組織)が細菌やウイルスに感染して炎症を起こす病気です。発症すると、全身の倦怠感、発熱、喉の痛みなどの症状が現れます。扁桃は、呼吸によって鼻や口から侵入する微生物(細菌やウイルス)から体を守る重要なバリアの役割を果たしています。
気管支炎
気管支は喉から肺へと続く空気の通り道です。ウイルスや細菌が気管支に感染すると、気管支炎が発生します。
鼻や喉に感染がある場合は鼻炎や咽頭炎と称されますが、気管支への感染は気管支炎と呼ばれます。さらに細い気管支で炎症が起こると「細気管支炎」と称され、これは呼吸障害を重篤化させる可能性があるため注意が必要です。
気管支炎や細気管支炎の多くはウイルス感染が原因で、RSウイルス、ライノウイルス、インフルエンザウイルス、ヒトメタニューモウイルスなどが関与します。細菌感染による気管支炎の原因としては、黄色ブドウ球菌、A群β溶血性連鎖球菌、マイコプラズマや百日咳があります。
マイコプラズマ肺炎
マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマという細菌によって引き起こされる肺炎です。初めて聞く方には心配に感じられるかもしれませんが、「元気な肺炎」と呼ばれ軽症ですむことが多い病気です。
主に小学生以上の子供に多く見られ、3歳未満の幼児にはあまり見られず、1歳未満では非常に稀です。クラス内で流行することがあり、咳や痰の飛沫による感染が主な伝播方法ですが、2~3週間という長い潜伏期間を持つ感染症です。家族の中で一人が感染すると、その2~3週間後に別の家族が感染することも珍しくありません。
マイコプラズマに感染しても、全ての人が肺炎を発症するとは限らず、マイコプラズマ感染症の3~10%が肺炎を発症すると言われています。
インフルエンザ
インフルエンザはインフルエンザウイルスによる感染症で、主に冬季に流行します。発症すると38℃以上の高熱、寒気、頭痛、関節痛、全身の倦怠感、筋肉痛などの症状が現れます。特に小さなお子様は症状が長引くことがあり、熱性けいれんや急性脳炎・脳症を引き起こすこともあります。意識障害やせん妄、異常行動なども見られるため、高熱時には子供の様子を注意深く観察する必要があります。抗インフルエンザ薬を早期に使用することで、症状の緩和が期待できます。当院ではワクチンによる予防接種も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
溶連菌感染症
A群β溶連菌という細菌による感染症です。喉の激しい痛み、高熱、全身の倦怠感などの症状を引き起こします。喉の痛みは非常に強く、「唾を飲むのも辛い」と感じるほどです。さらに、舌がぶつぶつと赤く腫れ(イチゴ舌)たり、体に赤い発疹が現れたりすることもあります。放置するとリウマチ熱や急性糸球体腎炎などの合併症を引き起こすリスクがあるため、速やかな治療が必要です。
RSウイルス感染症
RSウイルス感染症は、乳幼児における気道感染症の主要な原因となるウイルスです。RSウイルスの「R」はRespiratory(呼吸の)を意味し、このウイルスは呼吸器系に感染します。感染力が非常に強いため、ほとんどの子どもが2歳までに感染し、一度感染しても完全な免疫ができないため、繰り返し感染することがあります。
潜伏期間は2~8日で、「発熱」、「鼻汁」、「咳」といった風邪のような症状が出ます。通常は数日から1週間程度で良くなりますが、重症化する場合もあり注意が必要です。
アデノウイルス感染症
アデノウイルスは、その型によって体の異なる部位に感染し、多様な症状を引き起こすウイルスです。
風邪のような呼吸器症状をはじめ、目に感染すると目やにやかゆみを伴う流行性角結膜炎、喉の痛みと目の充血が特徴の咽頭結膜熱(プール熱)、急性胃腸炎による嘔吐や下痢などがあります。
特に夏季にはプール熱が流行することが多いですが、これはプールの水やタオルを介して感染が拡がるためです。しかし、アデノウイルス感染は夏に限定されず、一年中注意が必要な病気です。
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
おたふく風邪は、ムンプスウイルスによって引き起こされる感染症です。飛沫感染や接触感染を介して発症します。
この病気は、特に保育所や幼稚園で集団生活を始めた6歳以下の子どもに多く見られ、50%以上が感染します。おたふく風邪の典型的な症状には、耳の下(耳下腺)や顎の下(顎下腺)の腫れがあります。
多くの場合、腫れは左右対称に現れますが、片側だけに見られることもあります。腫れは通常1~3日で最大になり、約1週間で収まります。また、発熱も見られますが、通常は3~4日で解熱します。当院ではワクチンによる予防接種も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
川崎病
川崎病は、子供に発症する比較的一般的な病気で、適切な診断と治療が行われない場合、深刻な合併症を引き起こす可能性があります。
この病気は、地名ではなく、1967年に川崎富作医師によって発見されたことに由来しており、発熱、目の充血、唇や喉の発赤、首のリンパ節の腫れ、皮疹、手足の発赤・腫れなどの症状が特徴です。川崎病の原因はまだ明確には解明されていませんが、ウイルスや細菌の感染後に免疫系が過剰に反応し、全身の血管に炎症を引き起こすと考えられています。
特に日本人などのアジア系の人種に多く見られる病気です。原因不明な発熱がみられる場合は川崎病の可能性もあるため、受診をお願いします。
食物アレルギー
食物アレルギーは、特定の食品成分に対する免疫系の過剰反応で、食べるだけでなく触れたり吸い込んだりすることでも症状が現れることがあります。
この状態は乳幼児に特に多く見られ、乳児アトピー性皮膚炎などの即時型食物アレルギーがその一例です。その他にも、口腔アレルギー症候群、食物依存性運動誘発アナフィラキシー、新生児・乳児消化管アレルギーなどがあります。小さなお子様の健康な成長を支えるためには、栄養不足に注意しつつ適切な治療が必要です。
副鼻腔炎
副鼻腔は、顔の骨にある空洞で、粘膜に覆われており、鼻と繋がっています。この部分で炎症が生じる病気を副鼻腔炎と言います。主な原因はウイルスや細菌の感染、アレルギー反応などです。
風邪を引くと、鼻の粘膜が炎症を起こし、それが副鼻腔に広がることで副鼻腔炎になります。この急激な炎症を「急性副鼻腔炎」と呼び、1~2週間の治療で改善することが多いです。しかし、放置すると症状が悪化し「慢性副鼻腔炎」になることがあります。慢性の場合は治療期間が長くなります。
子供の副鼻腔は2歳から発達し始め、17歳で成熟しますが、発達段階では鼻(腔)との交通路が短いため病原菌が容易に到達しやすく、副鼻腔の空間も狭いため空間全体に炎症が生じやすいので注意が必要です。
花粉症
以前は花粉症といえば大人の病気でしたが、最近では子どもの花粉症が年々増加しています。
スギ花粉症においては、5~9歳の約30%、10~19歳の約50%が花粉症という報告もあります。
特に小さな子どもは、大人とは異なり症状を症状と捉えられず、言葉でうまく伝えられないため、見落とされているケースが少なくありません。毎年決まった季節に鼻水・鼻づまり・くしゃみが続く場合、風邪でもないのに鼻の症状が引かないという場合には、お早めに当院にご相談ください。
小児ぜんそく(気管支喘息)
気管支喘息は、呼吸困難を引き起こし、息を吐く際に特有のヒューヒュー、ゼーゼーという音がする病気です。この音は「喘鳴(ぜんめい)」と呼ばれ、気管支の壁が肥厚し内径が狭まることで発生します。よく聞く病名ですが、適切な治療が行われなければ、大人になっても症状が続き社会生活に影響を及ぼしたり、最悪の場合は命を落としたりする、実は怖い病気です。症状がなくても空気の通り道(気道)に炎症が続いている場合があり、継続的な治療と急性増悪を起こさないための予防が必要です。
子どもの中耳炎
子供の耳管は大人よりも短く水平になっているため、鼻や喉の病原体(約8割が細菌、2割がウイルス)が中耳(鼓膜の内側)に侵入し、中耳炎が発生しやすいとされています。特に6ヶ月~2歳の間に発症しやすく、3歳までには約80%の子供が一度は中耳炎を経験すると言われています。
中耳炎は子供に多い病気ですが、軽視してはなりません。治療を怠ると、症状が慢性化し、繰り返し発症する可能性があります。そのため、早期の医療対応が重要です。中耳炎の主な症状には、耳の痛み(約70%)、発熱、耳だれ(約10%)があります。風邪のような症状で受診した際に、急性中耳炎と診断されることも少なくありません。
乳幼児では、不機嫌さ、耳を触る行動、突然の泣き出し、泣き止まない、ミルクを飲まないなど、通常と異なる様子が見られた場合、中耳炎の可能性があります。中耳炎が進行すると、鼓膜の奥に膿が溜まり、鼓膜が破れて耳漏(耳だれ)が発生することがあります。さらに悪化すると、急性乳様突起炎、髄膜炎、脳膿瘍などの重篤な合併症を引き起こすリスクがあります。
ウイルス性胃腸炎
もしお子様が急に嘔吐や下痢をするようになったら、それは「ウイルス性胃腸炎」の可能性があります。この病気は「お腹の風邪」とも呼ばれ、小児科で診断される病気の中で風邪に次いでよく見られます。
秋から春にかけて特に多く見られる感染症で、ウイルスが胃や腸に侵入して症状を引き起こします。ロタウイルス、ノロウイルス、アデノウイルスなど、様々なウイルスが原因となります。病原体によって症状には多少の違いがありますが、一般的には嘔吐、下痢、腹痛、発熱などが主な症状です。
子どもの便秘
便秘症は「よく聞く病気でたいしたことはない」と思われがちですが、ほっておいてよい病気ではありません。放置していると悪循環を繰り返し症状が悪化し、「巨大結腸症(腸が異常に膨らむ)」や「遺糞症(おもらしをしてしまう)」になってしまうこともあります。子どもでも珍しいことではなく、10人に1人かそれ以上と考えられています。適切に治療を行えば数日から1~2か月で週に3回以上便が出る状態になりますし、治療を続けていれば1~2年で治ることもあります。早く治療を始めたほうが、後の経過が良くなります。治療薬も複数あるので、お子さんの状態にあった治療法を提案させていただきます。ぜひご相談ください。
起立性調整障害・不登校
起立性調節障害は、身体全体のバランスを整える自律神経機能が低下している状態です。自立神経は心臓や脳、全身の血液循環、水分栄養の消化吸収、体温、睡眠などのバランスをコントロールしているため、症状が疲労感、起床の困難、頭痛、目眩、立ちくらみ、腹痛といったように多岐にわたります。これらの症状は午前中に顕著で、午後にはしばしば和らぎますが、周囲から「さぼっている」「甘え」と誤解されることがあります。
発症したお子様は「学校へ行きたい」と願いつつも、体調の不良から行けない苦しみや不安を感じています。
上記の症状でお困りの際にはぜひ一度ご相談ください。
内科で診察可能な疾患
感染症について
感染症は、ウイルスや細菌、マイコプラズマなどの病原体が鼻やのどの粘膜に感染することで発生します。これにより、発熱、咳、のどの痛み、鼻水、頭痛、関節痛、筋肉痛といったさまざまな症状が現れます。ほとんどの感染症はウイルスによって引き起こされますが、場合によっては細菌やマイコプラズマが原因となることもあります。
特に日常的に耳にする「風邪(感冒)」も、こうした感染症の一つです。風邪は主にウイルスが原因となり、特効薬は存在しないため、症状に対する対症療法が中心となります。当院では、風邪による発熱や咳、のどの痛みといった症状に対し、解熱剤や鎮痛剤、鎮咳去痰薬などを用いて症状を緩和し、患者様の状態に合わせた治療を行っております。
症状が重く、食事や水分が摂取できない場合には点滴治療が必要になることもあります。また、細菌感染が併発していると判断された場合には、抗生物質を使用します。
当院では、風邪だけでなく、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症、マイコプラズマ感染症といった他の感染症にも対応しております。発熱や咳、のどの痛みなどの症状が続く場合や、ご自身での判断が難しい場合は、ぜひ当院にご相談ください。患者様の症状に応じた最適な治療法をご提案いたします。
生活習慣病
生活習慣病とは、食事や運動、休養、飲酒・喫煙といった生活習慣(の乱れ)を主な原因として発症・進行する病気の総称です。
よく知られたものに、2型糖尿病・高血圧・高脂血症(脂質異常症)・高尿酸血症などがあります。また広い意味では、動脈硬化が進行して起こる狭心症や心筋梗塞、脳卒中、大腸がんなどの一部のがん、アルコール性肝炎、歯周病なども、生活習慣病に含まれます。
「生活習慣」は良くも悪くも自覚しにくい性質を持ち、生活習慣病と診断されて初めて「悪い生活習慣を送ってきたことを知った」という方が少なくありません。少なくとも年に1度は健康診断や人間ドックを受け、生活習慣病の予防と早期発見・早期治療に努めましょう。また保護者様は、お子様の生活習慣にも気をつけてあげてください。子どもの頃に身につけた生活習慣は、将来的な生活習慣病のリスクを大きく左右します。
高血圧
診察室での血圧が140/90mmHg以上、ご家庭での血圧が135/85mmHg以上の場合に、高血圧と診断されます。血流が常に血管に大きな負荷をかけている状態であるため、血管が硬くもろくなる動脈硬化が進行します。さらに動脈硬化は、狭心症や心筋梗塞、脳卒中のリスクを高めます。一方で高血圧にはほとんど自覚症状がないため、早期発見のためには健康診断等における定期的な血圧の測定が重要となります。治療では、塩分摂取量を抑える食事療法、適度な運動を習慣化する運動療法が中心となります。食事療法・運動療法で十分な効果が得られない場合には、血圧を下げる薬を用いた薬物療法を導入します。
高血圧と診断された方は、ご自宅で毎日、決まった時間帯に血圧を測定し、記録するようにしましょう。通院の際には、その記録をご持参ください。
高脂血症(脂質異常症)
2型糖尿病、高血圧、高尿酸血症とともに、代表的な生活習慣病に数えられます。中性脂肪やLDL(悪玉)コレステロールの値が高すぎる、またはHDL(善玉)コレステロールの値が低すぎる状態です。自覚症状はほとんどありませんが、放置していると動脈硬化を進行させ、狭心症や心筋梗塞、脳卒中のリスクを高めます。
健康診断などで数値の異常を指摘された場合には、お早めに当院にご相談ください。
当院で行う検査
アレルギー検査
問診の結果、アレルギーの可能性があると判断された場合は、アレルゲン特異的IgE抗体を測定する血液検査を実施します。この検査だけでは確実性に限界があるため、食物アレルギーが疑われる場合は食物経口負荷試験も選択肢の一つになります。これは、アレルギー反応を引き起こす食物を摂取し、症状が出るかを確認する検査で、食物アレルギーの診断や、どれだけの量を安全に摂取できるかの耐性を調べるために行われます。気になる症状が見られた際は、どうぞお気軽に当院をご利用ください。
乳幼児健診
赤ちゃんの健やかな成長と発達を確認し、親御さんが抱える不安や疑問を専門家に相談できる重要な健診です。医師や保健師、助産師、栄養士など、様々な分野の専門家が、赤ちゃん1人ひとりに合わせたアドバイスを提供します。
この健診は、乳児健診や乳幼児健診とも呼ばれ、子供の成長をチェックするだけでなく、育児に関する相談にも応じています。定期的な受診が推奨されています。
健診で何か異常が見つかった場合は、無料でさらに詳細な検査を受けたり、専門医による診察を受けたりすることが可能です。
迅速検査・血液検査・尿検査
子どもは何らかの感染症で受診される方が多いです。迅速検査キットなどを用いて病原体の同定、適切な治療、予想される経過の説明に努めます。発熱期間が長ければ細菌感染も考える必要があり、血液検査を実施し白血球の数や炎症の値(CRP)を院内でチェックします。血尿や体(特に足)のむくみなどは尿検査で異常がないかチェックしていきます。
X線検査
主に胸部や頭部を撮影します。胸部では肺炎や無気肺、気胸、心臓のサイズチェックなどを行います。頭部では副鼻腔炎や頸部膿瘍(首の中の細菌感染)の有無などを確認します。
当院の予防接種について
母親から受け継いだ免疫は、子供の成長に伴い徐々に失われ、生後6ヶ月を超えると病気にかかりやすくなります。予防接種は、このような免疫の減少期にも病気を防ぎ、症状を軽減するために行われます。現在、様々な予防接種が推奨されており、どのワクチンを受けるべきか迷う保護者も多いでしょう。予防接種の計画は複雑であり、親御さんだけで管理するのは困難です。どうぞ、お気軽に当院にご相談ください。