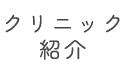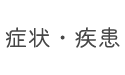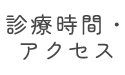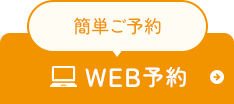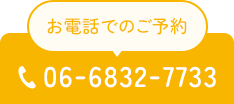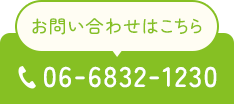予防接種とは
 感染症に対する免疫をつけるためにワクチンを接種することです。母親から受け継がれる免疫は、赤ちゃんが生後数ヶ月を過ぎると減少します。そのため、赤ちゃんが自ら免疫を形成し、感染症から身を守るためには予防接種が必要です。感染症には重篤化するものや、後遺症が起こるもの、時には生命を脅かすものもあります。お子さんの健康を守るためにも、積極的に予防接種を受けることが大切です。
感染症に対する免疫をつけるためにワクチンを接種することです。母親から受け継がれる免疫は、赤ちゃんが生後数ヶ月を過ぎると減少します。そのため、赤ちゃんが自ら免疫を形成し、感染症から身を守るためには予防接種が必要です。感染症には重篤化するものや、後遺症が起こるもの、時には生命を脅かすものもあります。お子さんの健康を守るためにも、積極的に予防接種を受けることが大切です。
予防接種を受けることで私たちは下記のような恩恵を受けることができます。
- 感染症にかかるリスクを減らす
- 感染したとしても重症化を防ぐことができる
- 感染症の流行を防ぐことができる
- 多くの人が予防接種を受けることで集団免疫効果が発揮され、先天性の免疫不全などで予防接種を受けることができない人を感染症から守ることができる。
現行の予防接種を受けることができなかった時代には感染症によって多くの子供たちの命が失われていました。ワクチンは、過去の感染症犠牲者や優れた医学者たちによってもたらされた、私たちが身近に享受できる医学の大きな功績の1つです。お子さんの健康、ご自身の健康、家族の笑顔のためにも予防接種は受けていただきたいと考えています。
【年齢別】
子どもの予防接種の種類
0歳
B型肝炎ワクチン(不活化)
B型肝炎はウイルスの感染によって肝臓の細胞が壊れ、その影響で肝臓の働きが悪くなる病気です。B型肝炎ウイルスは唾液や体液を介して感染する可能性があり、急性肝炎から劇症肝炎への移行や、慢性肝炎から肝硬変や肝がんなど生命を脅かす病気に進行するリスクがあります。ワクチンを乳児期に接種することでほぼすべての赤ちゃんが免疫を獲得することができます。
接種スケジュール
1歳未満の赤ちゃんには、3回のワクチン接種が推奨されます。最初の2回は生後2ヶ月から始めて4週間の間隔を空け、3回目は最初の接種から20週以上経過した後に行います。
小児用肺炎球菌ワクチン(不活化)
肺炎球菌による肺炎や、それに伴う髄膜炎や菌血症などを予防します。肺炎球菌は上気道の常在菌の1つであり、大人の10%、子供の20~40%の割合で鼻やのどから検出され、飛沫感染*1または接触感染*2し、中耳炎や肺炎を引き起こす原因となります。特に0歳代の子供は肺炎球菌による髄膜炎のリスクが高いため、早期の接種が推奨されます。
肺炎球菌は100以上の(血清型)に分類されていますが、現在日本で使用されている肺炎球菌結合型ワクチン(15価のバクニュバンス®、20価のプレベナー20®)は、主に15種類あるいは20種類の血清型の肺炎球菌による「侵襲性肺炎球菌感染症」の予防に効果があります。
*1:咳やくしゃみで飛び散った病原体を吸い込んで感染すること
*2:皮膚やおもちゃなどについた病原体を吸い込むことで感染すること
接種スケジュール
生後2ヶ月~4歳までの間に接種可能ですが、5歳以上6歳未満の子どもは任意接種として受けられます。
最初の3回は4週間の間隔をあけて接種し、生後12ヶ月~15ヶ月未満の間に4回目の接種を行います。
ロタウイルスワクチン(生)
ロタウイルスワクチンは、乳児期に重症化しやすいロタウイルス胃腸炎(激しい下痢、嘔吐、腹痛、発熱)を予防するためのものです。1価ワクチン(ロタリックス®)と5価ワクチン(ロタテック®)があり、当院では5価ワクチンを採用しています。ワクチンを接種することですべてのロタウイルス性胃腸炎を約80%予防し、重度のロタウイルス性胃腸炎に限るとその予防効果は約90%といわれています。
接種スケジュール
生後6週からワクチン接種が可能です。
2回または3回の接種を、それぞれ4週間の間隔を空けて行います。
Hib(ヒブ)ワクチン(不活化)
重症なHib感染症(細菌性髄膜炎や喉頭蓋炎)をほぼ100%予防します。2013年から定期接種のワクチンとなり、接種率が上昇したため2014年以降、規定回数のヒブワクチンを接種した小児で、重症なヒブ感染症の報告がありません。Hib(Haemophilus influenzae type b;インフルエンザ菌b型)は飛沫感染*1または接触感染*2し、中耳炎や肺炎を引き起こすことがあります。重症化すると、髄膜炎が発生し、後遺症や死亡に至ることもあります。
*1:咳やくしゃみで飛び散った病原体を吸い込んで感染すること
*2:皮膚やおもちゃなどについた病原体を吸い込むことで感染すること
接種スケジュール
生後2ヶ月~5ヶ月の間に3回接種し、1歳を超えた時点で追加の1回接種を行います。
5種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)・3種混合ワクチン(DPT)・2種混合ワクチン(DT)(不活化)
5種混合ワクチンはジフテリア*3、百日咳*4、破傷風*5、ポリオ*6、ヒブ(インフルエンザ桿菌)を予防し、3種混合ワクチンはジフテリア、百日咳、破傷風を、2種混合ワクチンはジフテリアと破傷風を予防するのに有効です。ワクチンで獲得した百日咳やポリオなどに対する免疫は、小学校に入るころには下がってくることがあります。下がりかけた免疫を高く保つため、就学前(5歳以上7歳未満)にこれらに対するワクチン(任意接種)をお勧めしています。
*4:突然激しく咳き込み、ヒューヒュー笛を吹くような咳がみられます。生後3ヵ月未満の乳児では息ができなくなり、ひどい場合は死に至ることもあります。ワクチンで免疫はできますが、時間が経つと効果が薄れていきます。
*5:破傷風菌による感染症です。主に傷口から入り込んだ破傷風菌が、毒素を出し、それが、さまざまな神経に作用します。口が開きづらい、あごが固くなるといった症状に始まり、歩きづらい、排尿・排便の障害などを経て、最後には全身の筋肉が固くなり体を弓のように反り返らせ、息ができなくなります。破傷風は、かかった人の約30%が死亡する非常に重い病気です。潜伏期間は3~21日程度です。ワクチンでしか免疫ができない病気で、国内では、高齢者を中心に毎年100人前後報告されています。
*6:感染者の糞便中に含まれるポリオウイルスに感染(糞口感染)して起こる病気です。かつて「小児まひ」と呼ばれ、国内でも大きな流行がありました。ワクチンが導入されるまで、毎年何千人もの患者さんや死亡者が出ていました。ポリオウイルスに感染しても、多くの場合は目立った症状はありません。きわめてまれに、麻痺(手足を動かすことができない状態や呼吸がしにくい状態)がおこり、一生障害が残ることがあります。特別な治療法はありません。ワクチン接種により予防ができる病気です。国内のポリオは根絶されましたが、世界の一部の地域では依然新しい患者さんが発生しており、それらの地域から国内にポリオウイルスが持ち込まれる可能性があるため、ワクチン接種により免疫を高く維持する必要があります。
接種スケジュール
生後2ヶ月から接種が始められます。
第1期は3回接種で、それぞれ3~8週間の間隔を空けます。3回目の接種から6か月以上あけて(標準的には6か月から18か月)4回目の接種を行います。
第2期は11~13歳未満で2種混合ワクチンを1回接種します。
BCG(生)
結核から赤ちゃんを守るために接種されます。結核は空気に漂う結核菌を吸い込むことで感染します。ただし、結核菌を吸い込んでもすべての人が発病するわけではありません。病気になるかどうかは、菌をもらった人の免疫と菌の量などの力関係によります。また、免疫力が低下した時に体の中に潜んでいた結核菌が再活性化して病気を起こすこともあります。免疫機能が未発達な小さなお子さんは重症化しやすく、結核菌が体中に広がる粟粒結核(ぞくりゅうけっかく)や、脳や脊髄を覆っている膜に感染する結核性髄膜炎を発症するリスクがあるため、予防が非常に重要です。
接種スケジュール
生後5ヶ月~8ヶ月未満の間に接種します。生後11ヶ月までに1回の接種を完了させる必要があります。
知っておいていただきたいこと~コッホ現象~
BCGの接種痕は接種後10日程度で発赤や膨隆がみられるようになり、1ヶ月で最も強くなり瘢痕化します。まれに接種後早期(1~7日、多くは3日以内)に接種部位に強い反応がみられることがあり、コッホ現象と呼ばれています。この現象はすでに結核に感染した方がBCG接種をうけられた場合にみられる反応で、乳児結核や未認知の家族内結核患者さんを発見するための重要な所見です。この現象がみられただけですぐに結核だと慌てる必要はありませんが、追加検査が必要なため、まずはご連絡をいただければと思います。
RSウイルス感染症の重症化を予防する注射製剤
RSウイルスは、乳幼児における呼吸器感染症の主要な原因となるウイルスです。特に早産児や心臓・呼吸器系の疾患を持つ赤ちゃん、免疫系が弱い赤ちゃん、ダウン症の赤ちゃんにとっては、感染が重症化するリスクが高まります。現在、RSウイルスに対する特効薬は存在しないため、予防が最も重要です。現在『シナジス』と『ベイフォータス』という抗体注射製剤が使用可能で、適応や投与頻度、効果持続期間に違いがあります。基本的には総合病院での使用が望ましいと考えますが、当院では現在『シナジス』のみ対応可能です。詳しくはお電話でお問い合わせください。
接種スケジュール
RSウイルスに特異的な抗体を含む「シナジス」を、流行期間中に月1回筋肉注射を行います。
生後6か月以降
インフルエンザ(不活化)
インフルエンザワクチンは、インフルエンザの発症と重症化するのを防ぐ効果に期待できます。重篤な脳の合併症としてインフルエンザ脳症(意識障害、けいれん、異常行動など)が知られており、最悪の場合、死に至ることもあります。時には後遺症が残ることもあり、当院としては重症化を予防できるワクチンの接種をおすすめしています。
接種スケジュール
現時点では 生後6ヶ月から12歳までは2回接種が必要です。13歳以上の方は1回の接種で済みます。1回目の接種は10月頃に行い、2回目は1回目から2~4週間後に接種します。
【2024年度】インフルエンザの予防接種について
当院では、インフルエンザの予防接種を以下の日程で実施を予定しております。
【接種開始日】
10月26日(土)より開始を予定しております。
【基本接種日時】
- 土曜日:14時~17時
- 火曜日:14時~15時45分
【追加接種日】
月・水・金の午後診(14時~15時45分)でも、空きがあれば接種可能です。
ご希望の方は直接ご相談ください。
注1:11月23日(土)は祝日のため休診となります。予防接種も行いません。
注2:最終接種日は12月7日(土)を予定しています。
【接種価格】
- 乳幼児(未就学児まで):3,000円/回
- 学童~青年(17歳まで):3,500円/回
- 成人(18歳以上、64歳以下):4,000円/回
【接種回数】
- 0歳6か月~12歳:2回接種(2回目は2~4週間後、推奨は4週間後です)
- 13歳~64歳:1回接種
【吹田市の助成】
① 中学3年生への助成
吹田市では、中学3年生のインフルエンザワクチン接種費用を一部助成しています。詳細はこちらをご確認ください。接種時には、必ず助成はがきを持参してください。はがきがない場合は助成が適用されませんので、必ずご注意ください。
② 65歳以上への助成
65歳以上の吹田市在住の方は、ワクチン接種費用の一部助成がございます。詳細はこちらをご確認ください。
【同時接種について】
他のワクチンとの同時接種を希望される場合は、接種日が上記と異なります。お電話にてご相談ください
1歳以降
おたふくかぜワクチン(生)
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎、ムンプス)はムンプスウイルスの感染症で、主に唾液を介して人から人に感染(飛沫感染)します。主な症状は発熱、耳下腺(顎の下の顎下腺のことも)の腫れ・痛みです。感染した人の3割は感染しても明らかな症状がでません。耳下腺(顎下腺)の腫れは症状がでて1~3日ごろがピークで、1週間ほどで良くなります。発熱は数日続き、頭痛、倦怠感、食欲低下、筋肉痛などを伴う場合もあります。
おたふくかぜは、無菌性の髄膜炎や脳炎・脳症、難聴、精巣炎・卵巣炎、膵炎などの合併症を伴うこともあります。また妊婦が感染すると流産のリスクが高くなります。日本耳鼻咽喉科学会からの報告では、2015~2016年の2年間に少なくとも348名がムンプス難聴となり、両耳難聴16名を含む300人近くに後遺症が残ったと報告されています。おたふくかぜワクチンを接種することで、おたふくかぜの発症や合併症を予防できるので、接種をおすすめします。
ちなみに諸外国からの報告では、おたふくかぜワクチンを1回定期接種している国でおたふくかぜの発症が88%減少し、2回定期接種している国では99%減少しています。
接種スケジュール
計2回の接種が推奨されています。日本小児科学会は、1回目を1歳になったら早めに、2回目を小学校入学前の1年間に接種することを推奨しています。
水ぼうそう(水痘)ワクチン(生)
水ぼうそう(水痘)は水痘帯状疱疹ウイルスに初めて感染して起こる病気で、発熱と一緒にまばらで盛り上がった発疹が頭部を含め全身にできます。このウイルスは患者さんの唾液や鼻水、水疱の中に存在し、それぞれ空気感染、飛沫感染、接触感染で感染します。病気が治ったあともウイルスは体から無くならず、神経の中に潜伏します。高齢になったり、体調不良で免疫が低下したりすると、ウイルスが再活性化し、神経に沿って発疹がでる帯状疱疹を発症します。このように水ぼうそう(水痘)と帯状疱疹は同じウイルスが原因で起こる病気のため、帯状疱疹の患者さんとの接触でもうつります。
最近の国内の調査では、1回のワクチン接種で水ぼうそう(水痘)にかかるリスクは80%弱減少し、2回接種で94%程度減少すると言われています。水ぼうそう(水痘)にかからないためには2回の接種が必要です。
接種スケジュール
1歳に達したら、最初の接種を行います。その後、最低3ヶ月の間隔を空けて2回目の接種をします。
麻疹・風疹混合(MR)ワクチン(生)
麻疹は初期症状として発熱、咳、鼻水、目の充血、目やにがでる病気です。一旦下がった熱が再び39℃を超える高熱となり、このころ口の中を見ると特徴的な白いぶつぶつ(コプリック斑)が見えます。その後皮膚に発疹(赤いぶつぶつ)が出現し全身に広がります。非常に感染力が強く、空気感染・飛沫感染・接触感染で感染します。症状が出る前日から解熱後3日を経過するまでは周りの人に感染させる可能性があります。合併症(肺炎や脳炎)がなければ7~10日程度で治りますが、肺炎と脳炎は麻疹の2大死因と言われており、医療の進んだ先進国であっても1,000人に1人は死亡する極めて重い感染症です。日本は2015年に麻疹が国内から排除されたと認定されました。しかし最近は麻疹の免疫を持たないまま麻疹流行国に行って感染し、帰国後に発症する人や麻疹流行国からの渡航者から感染して発症する人などがニュースになっています。
風疹は発熱、発疹(麻疹よりも淡い色の赤いぶつぶつ)、首の周りや耳の後ろのリンパ節の腫れが特徴的な病気です。数千人に一人の頻度で脳炎や血小板性紫斑病といった合併症を起こします。また感染しても症状が出ない不顕性感染が約15~30%あると言われています。風疹は風疹ウイルスを吸い込むことで感染する飛沫感染症で、潜伏期間は約2週間~3週間です。発疹が出現する前の1週間から出現した後の1週間は周りの人に感染させる可能性があります。
MRワクチンは麻疹と風疹の予防に用いられるワクチンです。1回接種で95%以上の人が免疫を獲得し、2回接種で99%以上の人が免疫を獲得します。
接種スケジュール
第1期:生後12ヶ月~24ヶ月未満の間に1回接種します。日本小児科学会は(当院としても)1歳になったらなるべく早めに1回目の接種を受けるように推奨しています。
第2期:5歳~7歳未満で小学校入学前の1年間(6歳になる年度の4月1日~3月31日)に1回接種します。
3歳以降
日本脳炎ワクチン(不活化)
日本脳炎は日本脳炎ウイルスによっておこる病気で、急な発熱、頭痛、吐き気などで発症します。急激に意識が低下して、けいれんや昏睡状態になり、命をおとす確率が約20~40%、後遺症を残す確率も高い病気です。日本脳炎ウイルスに感染した患者さんの100~1,000人に1人が脳炎になると言われています。日本ではウイルスを媒介するコガタアカイエカの活動時期に合わせて、夏から秋にかけて患者さんの報告があります。ウイルスを媒介する蚊によって感染するため人から人への感染はありません。
計4回のワクチンを接種することで日本脳炎にかかるリスクを75~90%減らすことができるとされています。
接種スケジュール
第1期:生後6ヶ月~90ヶ月未満の子供に対して3回接種します。
第2期:9歳以上13歳未満の子供に1回接種します。
標準的には、第1期の初回接種は3歳時に6日以上(標準的には6~28日)の間隔をおいて2回接種します。初回接種から6か月以上間隔をあけて(標準的には約1年後に)1回追加接種します。第2期は、9歳以上13歳未満(標準的には9歳)で1回接種します。
中学生以降
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(不活化)
ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染は、子宮頸がんや良性のいぼ(尖圭コンジローマ)などの原因になります。このウイルスは皮膚と粘膜が直接触れることによって感染します。性器病変を起こすものは、通常性行為によって感染します。HPVは100種類以上の型がありますが、皮膚に感染するものは皮膚型ウイルス、粘膜に感染するものは粘膜型ウイルス と呼ばれます。このウイルスは皮膚や粘膜のごく表面にのみ存在するため、私たちの免疫の仕組みから逃れ、感染しても抗体を作るような防御反応がほとんど起こりません。このために持続感染が起こってしまうと考えられています。そして持続感染した人の一部に、子宮頸がんなどの病気が起こります。
17歳未満でHPVワクチンを接種すると子宮頸がんの88%を防ぐと報告されています。 女性の重要なライフイベント期に発症率が高まるため、10代からのHPVワクチン接種と20歳からの定期的な検診が非常に重要とされています。
子宮頸がん:日本では毎年約11,000人の女性が子宮頸がんにかかり、約2,900人が死亡しています。20代後半から患者数が増え、40歳前後でピークになります。HPVには多くの型がありますが、その中でも少なくとも15種類はがんを起こす高リスク型と呼ばれ、特に16型と18型が子宮頸がん全体の3分の2以上の原因となります。
子宮頸がん以外のがん:女性には子宮頸がん以外にも、膣、外陰部、肛門、そして口の中や咽頭(のど)のがんを起こします。同様に男性にも陰茎、肛門、そして口の中や咽頭のがんを起こします。
尖圭コンジローマ:カリフラワー状の良性のいぼが性器の周りにできる病気です。
接種スケジュール
定期接種は小学校6年生から高校1年生相当の女子が対象です。当院で扱っている9価ワクチン(シルガード®9)は9歳以上であれば任意接種(自費負担)も可能です。
~15歳未満で開始した場合~
15歳未満に1回目の接種を開始した場合は、2回接種で終了することができます。2回目の接種は1回目から6か月の間隔を開けて行います。最短5か月の間隔があけば接種が可能ですが、5か月未満で2回目を接種してしまうと、3回目の接種が必要になりますのでご注意ください。
~15歳以上で開始した場合~
15歳の誕生日以降に1回目の接種を開始する場合は、3回接種になります。接種間隔は1回目と2回目の間は1か月以上、2回目と3回目の間は3か月以上あけて接種します。
これまで医療現場で働いてきて、子育て中の方や、お仕事でキャリアを積まれいよいよこれからといった方などが若くして子宮頸がんになり、命を落とされてしまう姿を見てきました。ご本人やそのご家族の悲しみは筆舌に尽くし難いものです。 私は小児科医、そして子を持つ親として、このワクチンは子どもの将来のリスクを減らせるものの1つと考えています。もちろん自分の娘たちにも有効性や安全性、副反応をしっかり説明し、接種してもらいたいと考えています。
もしいま接種可能な年齢で、接種を悩まれている方(親御さん含め)は話だけでも構わないので、ご相談いただければと思います。
出典:日本小児科学会の「知っておきたいわくちん情報」
https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/VIS_A-souron_20250228.pdf
当院が取り扱っている
予防接種一覧
定期接種と任意接種の違い
 期接種は予防接種法に基づき行われます。感染力が強くかつ重症化しやすい疾患に対するワクチンが提供されるため、指定された時期に接種することが望ましいですし、対象期間内であれば無料で受けられます。対象地域は吹田市だけでなく、周辺地域も含まれます。任意接種は親御さんが受けるかどうかを決めることができるもので、費用は自己負担です。定期接種の推奨期間を過ぎた場合の接種も、任意接種に該当します。定期接種に比べて重症化リスクは低いものの、重症化する感染症や海外で定期接種とされるワクチンもあるため、可能であれば任意接種も受けることが望ましいとされています。
期接種は予防接種法に基づき行われます。感染力が強くかつ重症化しやすい疾患に対するワクチンが提供されるため、指定された時期に接種することが望ましいですし、対象期間内であれば無料で受けられます。対象地域は吹田市だけでなく、周辺地域も含まれます。任意接種は親御さんが受けるかどうかを決めることができるもので、費用は自己負担です。定期接種の推奨期間を過ぎた場合の接種も、任意接種に該当します。定期接種に比べて重症化リスクは低いものの、重症化する感染症や海外で定期接種とされるワクチンもあるため、可能であれば任意接種も受けることが望ましいとされています。当院で行っている定期接種
- ロタウイルス
- B型肝炎
- 麻疹風疹
- 水痘
- 小児肺炎球菌
- ヒブ(Hib)
- 結核(BCG)
- ポリオ
- 日本脳炎
- 二種混合(ジフテリア・破傷風)
- 五種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ(Hib))
- ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(子宮頸がんワクチン) シルガード®9
当院で行っている任意接種
- インフルエンザ(10月~12月のみ)
- 高齢者肺炎球菌
- 帯状疱疹(シングリックス)
- 風疹
- おたふくかぜ
予防接種の流れと注意点
接種日当日の持参物
母子手帳
予防接種の際には必ずお持ちください。母子手帳をはじめ、下記の持ち物が確認できない場合は、予防接種を受けられなくなります。
保険証・診察券
母子手帳や予防接種予診票、接種票とご一緒に、健康保険証と当院の診察券(お持ちの場合)もお持ちください。
予防接種予診票 兼 接種票(定期接種)
定期接種を受けるために必要な書類です。
予防接種問診票
事前にご記入いただくと、受診がスムーズに進みます。
当日の流れ
1朝の体調確認
お子さんの場合は赤ちゃんの健康状態を注意深くチェックしてください。発熱、咳、鼻水がないか、ミルクの摂取量や便の状態に異常がないかを確認することが大切です。また、朝に赤ちゃんの体温を計測し、37.5℃以上の場合は予防接種が受けられないことがあるので、その際は当院へご連絡ください。
230分前までに授乳
予防接種の予約時間の30分前までには授乳を完了させてください。予防接種の痛みで嘔吐する可能性があるので、ロタウイルスワクチンは経口摂取するため、服用直後に嘔吐すると再接種が必要になる可能性があるので、直前の授乳は避けてください。また、赤ちゃんが不機嫌になったり、交通の遅延が発生したりすることもありますので、予約時間に遅れないように余裕を持って出発していただけますと何よりです。
3 受付
受付では、予防接種を受けるために来院したことをお伝えいただき、予診票、母子手帳、健康保険証、乳幼児医療証をご提示ください。
4接種
予防接種を受けた後は、アナフィラキシーと呼ばれる重大な副反応が発生しないかを確認するために、病院でしばらく体調を観察させていただく場合がございます。アナフィラキシーは接種後30分以内に起こることが多いため、安全のために院内で待機していただくことがあります。待機が不要な場合はその旨をお伝えします。
5 接種後の体調観察
予防接種後に安定した状態を保っている場合、お風呂に入っていただいて大丈夫ですが、接種した部分を激しく擦らないよう注意し、長風呂は控えてください。乳児の場合、母乳やミルクは予防接種後30分が経過してから与えることが望ましいです。嘔吐した際に、それが副反応によるものかどうかを判断するためです。
おうちでの過ごし方
体調に変化がないか、特に発熱やじんましんなどの発疹の有無、呼吸の様子に注意して観察してください。普段と異なる様子が見られた場合は、遠慮なくお問い合わせください。
発熱しても大丈夫?
子供の予防接種後の副反応

予防接種後の発熱は珍しくありません(初回では3~5%)。通常は1日以内に自然に解熱します。接種後の症状が軽い場合はご自宅で様子を見ても大丈夫ですが、ぐったりしている、泣き声が弱い、哺乳量が減少している、尿量が少ないなどの症状があれば、早めに医療機関を受診してください。特に生後3ヶ月未満の赤ちゃんは感染症に対する抵抗力が弱いため、注意が必要です。
また、接種部位の赤みや腫れなどの局所反応も珍しくなく、通常は数日で自然に治まります。ただし、症状がひどい場合は医療機関を受診してください。
当院の予約方法
 当日は窓口で直接順番を取ることもできますが、お待ちいただく可能性がありますので、事前のご予約をお勧めします。
当日は窓口で直接順番を取ることもできますが、お待ちいただく可能性がありますので、事前のご予約をお勧めします。